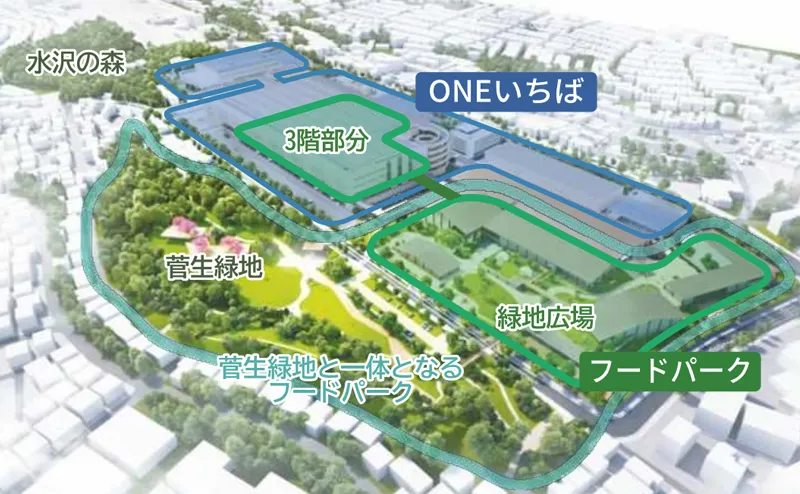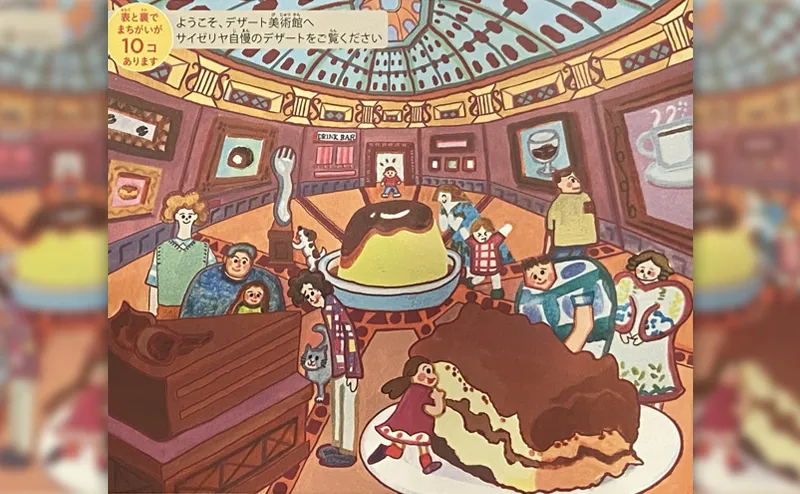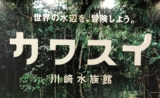毎年、会社の初詣で参拝している「川崎大師(かわさきだいし)」。ちょっと前になるけれど、1月下旬の平日にプライベートで参拝してきたのでご紹介します。
川崎大師とは?
1128年に開創し、2019年で891年の歴史がある「川崎大師 平間寺」。成田山新勝寺(千葉県成田市)、高尾山薬王院(東京都八王子)とともに、真言宗智山派(ちさんは)の大本山の寺院でもあります。
正式な名称は、「金剛山 金乗院 平間寺」。
通称、厄除弘法大師(やくよけこうぼうだいし)、または川崎大師。

古くから「厄除けのお大師さま」として知られれ、毎日、護摩祈祷を修行し、厄除け、家内安全、商売繁昌、健康長寿など、皆さまの諸願成就をお祈りしています。御本尊は「厄除弘法大師」。
川崎大師へのアクセスは?
正月三が日の「川崎大師」は、それはそれは混雑します。
がしかし、1月下旬ともなると僕も初体験。
電車好きな3歳の息子が「京急大師線」と「川崎大師」に食いつき、両方に行きたい症候群に駆られたので、保育園を早めに切り上げて行ってきました。それが今回の経緯。
最寄駅、京急大師線「川崎大師駅」

というわけで、最寄駅はそのままですが京急大師線「川崎大師駅」。
他の駅にはない書体の駅看板。威風堂々としちょるね。

とてものどかな雰囲気です。
[混雑が予想される日の場合]
行きは「川崎大師駅」で降りますが、帰りはもう1つ先の「東門前駅」から乗った方がいいですよ。座れる確率が増します。両駅とも川崎大師からは同じような距離にあります。
川崎大師駅からのルート
駅の改札を出るとすぐ、

「表参道 厄除門」が見えます。
行きましょう。

道なりにずっと歩いて行き、おそば屋さん「松月庵」を右折すると、仲見世です。
行っちゃいましょう。

もうすぐ仲見世も閉まるよーって時なのに、チラホラ人がいました。多いんだね。
正月三が日は比較にならないほどエゲツないし、元旦はそれこそ仲見世が人で埋まります。

仲見世の奥から入口側を見た写真。
振り返れば、

そびえ立つ、大山門。

行っちゃいましょう。
くぐっちゃいましょう。
川崎大師の境内は?

そこそこ参拝者がおるね。

手水舎。
左側にはお護摩受付所。
企業や個人でお護摩札に名前を書いてもらい、それぞれのお願いごととともにお護摩で諸願成就をお祈りしてもらいます。川崎大師でとても人気あるもので、通年やっていることとはいえ、1月下旬の平日でもこんなに多くの人がいるのかと驚き。
川崎大師の御朱印は?

先ほどのお護摩受付所の左隣にあります。

ちなみに川崎大師の御朱印は4種類あります。
メイン?の御朱印は、ここ「護持志納受付所」と「大本堂」で拝受できる。

こちらは不動堂。
大本堂を正面に見て左奥にあります。
川崎大師の経蔵

大本堂の手前にある「経蔵」。
平成16年大開帳奉修記念事業として落慶されました。
経蔵には中国最後の木版大蔵経「乾隆版大蔵経」7240巻が収蔵されています。
御本尊・説法釈迦如来の前に置かれた五鈷杵には、金箔を奉納する事ができ、この奉納によって仏様とご縁を結ぶことができます。

木版大蔵経「乾隆版大蔵経」が7240巻あるらしい。
理解できたのは“7240”という数字だけ。

すばらしい天井画。
その他の境内写真

つるの池

つるの池に架けられた、やすらぎの橋。
つるの池に架けられた、やすらぎの橋、越しに見える降魔成道釈迦如来像。

八角五重塔。
今まで何10回も行っている川崎大師だけど、一番驚いたのが、

屋台の数。
1月下旬なのにまだこんなに屋台が出ているの…?
まさか年中、屋台が出ているということではないよね…?
恐ろしきかな川崎大師。

息子も川崎大師を満喫。

帰りはすっかり暗くなった。17時にはほとんど閉まっていた。

光る川崎大師駅。
“驛”がカッコいい。

ここまでこだわる書体。
[混雑が予想される日の場合]
行きは「川崎大師駅」で降りますが、帰りはもう1つ先の「東門前駅」から乗った方がいいですよ。座れる確率が増します。両駅とも川崎大師からは同じような距離にあります。
川崎大師 平間寺
| 住所 | 〒210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急大師線『川崎大師駅』より徒歩9分 京急大師線『東門前駅』より徒歩8分 |
| サイト | 川崎大師Webサイト |